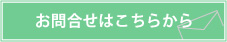軽視できない印刷コスト
プリンターで大事なのが画質。配るにしろファイリングするにしろ、資料は美しいに越したことはない。
ページプリンターの画質は、解像度の数値を調べれば分かる。解像度も必ずと言っていいほどカタログに記述してある。単位は「ドット」で、用紙の1インチ当たりにいくつのドットを描くことができるかの量を示したものだ。「dpi」(dot per inch)で示される場合もある。値が大きいほど、理論上は精細な印刷結果が得られる。600もしくは1200ドットであることが多い。文字を中心に印刷する限り、600ドットと1200ドットでは見て分かるほどの大きな差がないとみていい。
「9600ドット相当」といった具合に、1200ドット以上の数値をうたう製品も数多いが、これはドライバーソフトがドットの描き方を工夫し、1200ドット以上の点を描いたかのごとく見せかける工夫があることを意味する。文字ではその効果を感じづらいが、精細な写真を出力した場合には画質アップが期待できる。
3つ目の印刷コストも見逃せないポイント。ページプリンターは、印刷に用いる粉末状のトナーとドラム(感光体)などの消耗品を定期的に補充、交換する必要がある。消耗品が高価だったり耐用期間が短かったりすると、本体を安く買っても、運用でコストがかさんでしまう。
一例を挙げよう。わずか2円の違いだが、大量に出力する環境下では、3年間で約10万円も出費に差がついてしまう。長い目で考えれば、予算は絞らず、予算ギリギリで高性能かつコストの安い製品を選んだ方が賢明だろう。
印刷コストは、A4判用紙1枚に印刷した場合にかかる金額で示される。用紙代は含めず、消耗品をベースに算出した理論上のコストである。トナー代とドラム代を合計し、そのほか廃トナーボトルなどの消耗品がある場合はこのコストも加えたものだ。トナー代は、トナーカートリッジの価格をトナーが空になるまで印刷可能な枚数で割り算して求める。ドラム代は、ドラムの価格を耐用枚数で割り算して求める。カラープリンターはトナーカートリッジとドラムを4種類使うので4本分を合計する。
トナー代を計算する際には、業界の慣習として、紙一面に特定の濃度(5%)で印刷し続けると仮定している。オプションでお得な大容量カートリッジがある場合はこちらで算出するのが一般的なので注意しよう。
使い勝手にも注目せよ
以上3つを満たせばほぼ満足できる製品を選び出せるが、最後の「使い勝手」にも注目。例えば、トナー交換が複雑で手間取るようでは、日常の業務に差し障りが出てしまう。
ページプリンターの使い勝手を左右する代表的な要素を示した。どれもカタログの仕様表から読み取ることができるものばかりだ。
いくつかを紹介しよう。まず「給紙量の多さ」。ページプリンターには、できるだけ多くの紙を同時にセットできた方が重宝する。毎日50枚印刷するなら、給紙量が250枚と1250枚とでは、紙を補充する回数がだんぜん変わってくる。
カタログに書かれた標準状態でセットできる枚数は多くの場合、給紙カセットに手差しトレイの給紙量も加えたものだ。プリンターを複数人で使うつもりなら、増設カセットの活用の可否も調べたい。多くの製品は、オプションで増設カセットを用意しており、ページプリンターの下部に取り付けられる。カセットを複数段重ねられる製品では、1000枚以上に給紙量を増やせることがある。
「対応用紙の多彩さ」にも触れておく。オフィスでは、コピー用の普通紙(PPC用紙とも呼ぶ)が最も多く使われる。ただ、はがきなど特殊用紙に印刷することが欠かせない企業も多いはず。はがきやラベル紙はたいていのプリンターで印刷でき、問題ない。ただ厚紙や封筒、OHP用紙は、扱えなかったり、紙の厚さに制約があったりする場合が少なくない。ポスターや垂れ幕を作れる一辺が100cm以上ある長尺用紙も、対応製品が限られる。
以上、製品選びの4大ポイントを紹介した。ここから先は、価格帯別に代表的な製品を紹介しつつ、買い方のコツ見ていくことにしよう。
価格帯は大きく3つに分かれる
キヤノンとセイコーエプソンの実勢価格が20万円以下のモノクロ機について、印刷速度と価格の関係を示した。価格帯によって印刷速度が大きく変わるため、本記事では実勢価格が5万円未満の「低価格クラス」、5万~10万円の「普及クラス」、10万~20万円の「高性能クラス」と3つに分けて製品を紹介する
主なページプリンターメーカー
沖データ、キヤノン、コニカミノルタ ビジネステクノロジーズ、セイコーエプソン、ブラザー工業、リコー
プリンターの能力を左右する「印刷速度」
一般にページプリンターの印刷速度は1分当たり何枚を出力できるかで示す。ただこれは連続印刷時の最高速度で、実際の速度は、ウオームアップやデータ処理にかかる時間に左右され、遅くなることが多い
「画質」は解像度で決まる
解像度は、1インチ当たりにいくつのドットを描けるかを示す単位。600ドットか1200ドットの製品が多い。ただ文字を印刷する限りはその違いは分かりづらい
わずか数円の違いでも年間で見ると大きな差になる「印刷コスト」
カタログに表示されている印刷コストは、紙代を除き、各種消耗品の価格から計算して求めた値。製品によって違いは数円のレベルだが、大量に印刷する環境では、3年で10万円以上のコスト増になる場合があるので注意
満足度に影響する「使い勝手」
実際に使っていく上で、使い勝手の良しあしは大切なポイント。カタログから読み取ることができる使い勝手の要素を示した
給紙できる量は十分か?
標準カセットの容量が小さいと頻繁に用紙を補給する手間がかかる。増設カセットで最大何枚まで給紙量を増やせるかを確認したい
用紙の種類は豊富か?
業務で特殊紙へ印刷することがあるなら、対応する用紙の種類も要チェック。厚紙や封筒などは対応するものが限られたり使えなかったりする
低価格クラス
「印刷速度」を最優先して選んでOK
実勢価格5万円未満で買える低価格クラスは、ここ数年で最もコストパフォーマンスが向上した価格帯と言える。「安いから遅い」というのは過去のイメージで、印刷速度が20枚/分前後の製品が多くなってきた。一般的なオフィス文書を印刷する限り、多くの人はスピードが遅くてストレスを感じることはないだろう。安い製品なら2万円を切る価格で手に入るので、個人でも買いやすい。
低価格クラスの製品のほとんどは、A4判の用紙に対応したモノクロ機である。残念ながら予算5万円ではカラー機には手が届かない。A3判対応モデルの選択肢もほとんどない。B4判やA3判用紙に印刷できるのは、セイコーエプソンの「Offirio LP-S1100」などごく一部に限られる。2006年1月発売のLP-S1100は、発売から1年を経て実勢価格が定価の半値近くにたまたま下がった製品で、本来一つ上の普及クラス。A3判対応モデルを買うなら、製品が豊富な普及クラスに目を向けたい。
LAN端子を備えた製品が少なく、オプションでも端子を増設できない場合が多いので、プリンターをLANで共有したい場合は要注意。プリントサーバーを用意するとなると、結果として追加コストがかかる。
使い勝手の差はわずか
このクラスの製品を選ぶ際に重視すべきは、ずばり印刷速度である。製造コストが限られる低価格クラスの製品は、スペック的にどれも似通っており、使い勝手も含め大きな差がない。パソコンと同じ卓上に設置して使うことを想定しているため小型であるし、際立って稼働音がうるさい製品もまずない。給紙量は一人で使う分には十分な量の150枚以上をカセットにセットしておける。印刷コストも、出力数が1日10枚にも満たないのなら、目くじらを立てるほど負担額が変わることはない。
つまり、印刷速度で割り切って選んでも構わない。予算があるなら、ブラザー工業「HL-5250DN」やリコー「IPSiO SP 3100」のように、24枚/分で印刷できる製品がお薦めだ。
ただ前章で紹介したように、ウオームアップ時間やファーストプリント時間の数値も含めて総合的に速度を吟味することが肝心。例えばキヤノンの「Satera LBP3000」「Satera LBP3300」は、通常ウオームアップに20秒前後かかる製品が多い中、0秒で瞬時に通常モードに復帰するのがウリ。電源投入直後でも10秒以内に印刷が始まる。
見過ごしがちなのが、パソコンの推奨環境が指定してある製品が一部にあること。こうした製品では、パソコンがある一定以上のスペックを満たしていないと、プリンター本来の性能を発揮できない。これは、データ処理の一部をパソコン側で肩代わりする仕組みを採り入れているのが原因だ。製品選びの際には、動作環境について制約がないか、必ず一度確認したい。
このクラスのポイント
- ●ターゲットはA4判対応のモノクロ機
- ●「印刷速度」をチェックすべし
- ●文字中心なら「解像度」を重視しなくてもOK
- ●このクラスはパソコンのCPUが低性能だとスピードが落ちる場合がある
低価格クラスでは、製品のコストを下げるため搭載するCPUが低性能な場合がある。パソコンのCPU能力を借りることで印刷する都合上、パソコンのCPUが低性能だと印刷速度に支障がでやすい
各製品の仕様の見方
低価格クラス(5万円未満)
| 製品名 | メーカー | 価格 |
|---|
| MICROLINE 22L | 沖データ | 4万1790円(実勢価格は3万1000円) |
| Satera LBP3000 | キヤノン | オープン(実勢価格は1万9000円) |
| Satera LBP3300 | キヤノン | オープン(実勢価格は3万円) |
| PagePro 1350W | コニカミノルタ ビジネステクノロジーズ | 4万1790円(実勢価格は2万円) |
| Offirio LP-1400 | セイコーエプソン | 4万1790円(実勢価格は2万6000円) |
| Offirio LP-S1100 | セイコーエプソン | 8万3790円(実勢価格は4万円) |
| HL-2040 | ブラザー工業 | 4万2000円(実勢価格は1万8000円) |
| HL-5250DN | ブラザー工業 | オープン(実勢価格は3万5000円) |
| IPSiO SP 3100 | リコー | 6万2790円(実勢価格は4万8000円) |
普及クラス
選択肢にはカラー機も、速度差に注目
ページプリンターにも複合機化の波
インクジェットプリンターで主流になりつつある複合機タイプの製品が、ページプリンターでも急増している。複合機は、ページプリンターにコピーやスキャナー、ファクスといった要素を持たせた多機能機である。コピーを取ったりファクスを送ったり、1台数役をこなせる。スキャナーやコピー機を買いそろえるより安く済み、設置場所を節約できるのが魅力だ。
複合機の魅力はそれだけではない。スキャナーを活用して、文書をデジタル化することも可能なのだ。紙の文書をJPEG画像やPDFファイルに変換し、これを保存する機能をほとんどの製品が備えている。オフィスに散らばる文書をデジタルの形で保管すれば省スペース化にも役立てられる。
たいていの製品は、デジタル化した文書データをUSBケーブルで接続したパソコンに保存したり、電子メールに添付して特定のあて先に送信したりできる。一部の製品は、ファイルサーバーやWebサーバー、FTPサーバーにもアップロード可能だ。
使い勝手の良しあしが命
実勢価格20万円未満で買える代表的な複合機をまとめた。カラー対応の複合機は10万円以上してしまうが、モノクロ機なら10万円未満で買える。なお機能が多い分、同じ価格帯の単機能プリンターに比べると、複合機の印刷速度は概して遅くなる。
複合機を選ぶ作業は、少々複雑だ。ページプリンターを買う際に押さえるべき4つのポイント以外に、複合機としてのチェックポイントも加味しなければならない。ボタン類を操作したり、原稿をセットしたりと、複合機はプリンターを単体で使う機会が増える。つまり、よりいっそう使い勝手の良しあしが満足度を大きく左右する。例えば、ADF(自動給紙装置)がない製品では、大量のページをコピーまたはファクスする際に不便を感じる。
複合機は、できれば購入に際して、一度実機に触れて操作してみることをお勧めしたい。家電量販店で製品の取り扱いがないメーカーも、たいていは製品を操作できるショールームを開設している。
このクラスのポイント
- ●カラー機に手が届く
- ●エンジンの違いは速度に影響が出る
- ●設置スペースが足りないならA3判印刷はあきらめる
- ●カラー機にはエンジンの方式に2種類ある
カラー機の中には、モノクロの速度がカラーに比べて極端に遅い製品がある。「4サイクル式」と呼ばれるタイプがそれ。カラー印刷が低速な代わりにモノクロ印刷が高速な「4サイクル式」と、カラーもモノクロも速度が同じ「タンデム式」では同じ価格でも速度が違う。
設置スペースに見合う大きさかも確かめる
大きさがばらついているのが、普及クラスの製品の特徴だ。カラー機の場合、タンデム式は4サイクル式に比べて大型。もちろん対応する用紙がA3判かA4判かでも大きさは変わってくる。
複合機とは?
ページプリンターに、スキャナーやコピー、ファクスなどの機能を付加した製品のことを「複合機」と呼ぶ。「デジタル複合機」「オールインワンプリンター」と表記する場合もある
主な複合機型のA4判対応ページプリンター
普及クラス(5万~10万円)
| 製品名 | メーカー | 価格 |
|---|
| C5800n | 沖データ | 10万4790円(実勢価格は8万円) |
| Satera LBP5100 | キヤノン | 9万4290円(実勢価格は7万円) |
| magicolor 2530DL | コニカミノルタ ビジネステクノロジーズ | 10万4790円(実勢価格は7万円) |
| Offirio LP-V500 | セイコーエプソン | オープン(実勢価格は9万円) |
| Satera LBP3410 | キヤノン | 10万2900円(実勢価格は8万円) |
| Offirio LP-9100N | セイコーエプソン | 12万3900円(実勢価格は10万円) |
| LaserJet 4240 | 日本ヒューレット・パッカード | 直販価格は7万9800円 |
| HL-5280DW | ブラザー工業 | オープン(実勢価格は5万5000円) |
| IPSiO SP 6120 | リコー | 13万4400円(実勢価格は9万9000円) |
高性能クラス
LAN対応は当然、ぜひ欲しい両面印刷
最後に紹介するのが高性能クラスである。1分間に20枚以上印刷できる高速なカラー機も選べるのが魅力だ。高性能クラスのカラー機を購入すれば、カラー文書を大量に出力する場合でも遅くてイライラさせられることはまずないと言っていい。
モノクロ機なら、43枚/分の日本ヒューレット・パッカード「LaserJet 4250」のような、非常に速い印刷速度を誇る製品が手に入る。これは、100万円以上するデジタル複合機でコピーした場合に近い出力スピードだ。
高性能クラスの実勢価格は、10万~20万円。値は張るが、部課単位でに導入するページプリンターは、できればこのクラスから選びたい。複数人が共有したり、出力枚数が多かったりする環境下でも、高速なので安心して導入できるためだ。LAN端子付きの製品が大多数なので、LANへの接続も追加コストなく可能だ。
高性能クラスになると、製品ごとに使い勝手の面で差が顕著に表れる。使い勝手は、日常使い続ける上での満足度を大きく左右するので、わずかな差でも侮るべきではない。例えば印刷コストの小さな差は、年間で考えれば決して無視できないし、給紙量が少ないと紙を補給する回数が増えて不便に感じるだろう。
迷惑な騒音は出さないか
注目したいのは、自動両面印刷機能の有無である。自動両面印刷は、2ページ分の原稿を紙の表面と裏面に印刷し、通常2枚の紙を消費するところ、1枚で済ませるようにするものである。出力枚数が多いオフィスでは、用紙コストがかさみがちなだけに、ぜひ欲しい機能だ。用紙を補給する回数が半減するのも魅力だ。印刷時のレイアウトを工夫すれば、印刷コストの削減にもつながる。1ページに2ページ分の原稿を割り付けた上で両面印刷する。これで、印刷コストも抑えられる。一つ注意するとすれば、両面印刷時に印刷速度が大幅に落ち込む製品があることだ。
稼働音の大きさにも気を配るべきである。耳障りな騒音をまき散らすページプリンターでは、静かなオフィスの環境を乱してしまう。できるだけ稼働音の静かな製品が好ましい。
稼働音はデシベル(dB)と呼ばれる単位で表される。測定方法は、国際標準化機構(ISO)で定められている。具体的には、高さ75cmの位置にページプリンターを置き、1m離れた位置からマイク(高さは1.5m)で拾った音の大きさを稼働音とする。各メーカーは規格に沿った値をカタログに掲載しているのが一般的だ。
静かな事務所レベルの約50dB台の製品が多いが、中には60dB(普通の会話レベル)を超える製品もある。3dB違うと2倍、10dB違うと10倍も大きな音として聞こえるだけに、1dBの差も決して小さくない。
このクラスのポイント
- ●カラー機の選択肢が増える
- ●グループで使うなら「LAN」「両面印刷」対応機に
- ●「使い勝手」に大きな差あり
- ●印刷速度ばかりでなく、「使い勝手」の差にも注目
高性能クラスともなると、グループで活用するために購入するケースが多いはず。複数人で使い回すからこそ、使い勝手が悪いと快適に印刷はできない。LAN端子があればプリントサーバーの設置が不要になり運用が楽になるし、自動両面印刷機能が備わっていれば、印刷コストの大幅な削減につなげられる
侮れない稼働音の違い
オフィス内の数ある機器の中でも、ページプリンターの稼働音はうるさい部類に入る。最近は、待機時に無音になるなど、低騒音をうたう製品もある
高性能クラス(10万~20万円)
| 製品名 | メーカー | 価格 |
|---|
| C5900dn | 沖データ | 15万5400円(実勢価格は11万8000円) |
| C8600dn | 沖データ | 18万6900円(実勢価格は13万円) |
| N3500 | カシオ計算機 | 26万400円(実勢価格は15万2000円) |
| N6000 | カシオ計算機 | 26万400円(実勢価格は18万6000円) |
| Satera LBP5600SE | キヤノン | 20万7900円(実勢価格は15万8000円) |
| ECOSYS LS-C5030N | 京セラミタ | 26万400円(実勢価格は19万8000円) |
| magicolor 5440DL | コニカミノルタ ビジネステクノロジーズ | 23万9400円(実勢価格は14万8000円) |
| magicolor 7440 | コニカミノルタ ビジネステクノロジーズ | 29万1900円(実勢価格は16万8000円) |
| Offirio LP-S5500 | セイコーエプソン | 17万6400円(実勢価格は13万円) |
| Offirio LP-S7000 | セイコーエプソン | 20万7900円(実勢価格は18万8000円) |
| Color LaserJet 3000 | 日本ヒューレット・パッカード | 直販価格は11万9700円 |
| DocuPrint C 3200 A | 富士ゼロックスプリンティングシステムズ | 20万7900円(実勢価格は13万6000円) |
| DocuPrint C3050 | 富士ゼロックスプリンティングシステムズ | 15万5400円(実勢価格は11万円) |
| IPSiO SP C411 | リコー | 20万7900円(実勢価格は14万4000円) |
| IPSiO SP C810 | リコー | 31万2900円(実勢価格は20万5000円) |
| Satera LBP3970 | キヤノン | 15万5400円(実勢価格は11万8000円) |
| LaserJet 4250 | 日本ヒューレット・パッカード | 直販価格は18万6900円 |
| DocuPrint 3050 | 富士ゼロックスプリンティングシステムズ | 15万5400円(実勢価格は12万3000円) |
プロジェクター編
XGAで2000ルーメンが主流に
次に、データプロジェクターの使い勝手を向上させる付加機能について見ていこう。
自動台形補正で楽々準備
小型軽量の可搬型データプロジェクターを会議室に置きっぱなしにできる企業は少ないだろう。多くは普段棚などにしまっておき、必要なときに取り出して会議室へ持って行くという使い方になるはずだ。この場合、毎回使用前に会議室の広さや机の配置、スクリーンの位置に合わせて画像を調整する必要がある。こうした準備作業の手間を軽くする付加機能に注目したい。
まず注目したいのが、台形補正機能だ。一般にデータプロジェクターを、水平方向よりもやや上向きに傾けて投射すると、画像が台形になってしまう。これを補正し長方形にするのが台形補正機能だ。現行製品の大半で台形補正機能を備えてはいるが、ユーザーが画像を見ながらボタンを繰り返し押して調整する手動タイプと、机に置くだけで製品が傾きを検知し補正する自動タイプでは、使い勝手が大きく異なる。設置作業をひんぱんに繰り返すなら、自動台形補正はぜひ欲しい機能だ。多くはこれで十分だが、高価格帯の一部機種ではさらに、縦方向に加え横方向にゆがんだ画像を補正できる製品もある。こちらは会議室の形状の問題で、真正面からの投射が難しい場合などに重宝する。
最近増え始めているのが、壁色補正機能だ。もともとは学校向けに販売するデータプロジェクターで、教室の黒板をスクリーン代わりに使えるよう備えられた機能だ。最近は黒板色のほか、ベージュや茶色など複数の壁色に対応できるよう機能を拡充した製品が増えている。
冷却不要の製品も
会議や講演会の後、片付けの手間を軽減してくれる付加機能もある。一般にプロジェクターは、電源を切った後も冷却が終わるまでの数十秒~数分間はコンセントを抜けず、製品を机の上に置いたまま待つ必要がある。
しかしここ1~2年、この待ち時間を短縮するよう改良した製品が急速に存在感を増している。多くは今のところ、放熱性能を向上させて冷却運転の時間を短縮したり、冷却運転中にコンセントを抜けるようにしたりというものだが、大きく進歩を遂げた製品もある。セイコーエプソンの「EMP-1815」やNECビューテクノロジーの「NP60J」などのように完全に冷却運転を不要にした製品だ。会議室の予約終了時刻ぎりぎりまで打ち合わせが長引き、次の利用者に速やかに明け渡さなければいけないといった場合に助かる機能だ。
付加機能ではないが、準備時の手間という点で見落としがちなポイントがピントやズームの調整機能である。大半の製品では投射する画像を微調整するためにピントやズームの調整つまみを備えているが、メニュー画面でボタンを押して調整する仕組みになっている製品もある。こうした細かい使い勝手の違いはカタログからは読み取れないので、購入前に製品の貸し出しサービスを利用するなどして確認しておきたい。
16枚の画面を分割表示
このところメーカー各社が新たな付加機能として力を入れているのが、無線LAN機能だ。通常、アナログRGBなどの端子を使ってパソコンとデータプロジェクターをつなぐ必要があるが、無線LANを使うことでケーブルの持ち運びや接続作業が不要になったり、座席配置の自由度が高まったり、簡単に次の人へプレゼンを交代できたりするメリットがある。
無線LANで新たな使い方を提示した製品もある。松下電器産業の「LB-50NT」やセイコーエプソンの「EMP-1715」などのように、複数の画面を制御するものだ。投射画面を4~16分割して、複数のパソコンから無線LANで画像を受信し表示できる。逆に、1台のパソコンから複数のデータプロジェクターへ一斉に異なる画像を送信し表示させる機能もある。
なお、無線LAN機能を使うには、パソコンに専用ソフトウエアをインストールする必要がある。また静止画は問題ないが、動画を無線LAN経由で投射するとコマ落ちが発生するといった課題もある。無線LAN機能で選ぶならば、購入前に実機を借りて使い勝手を確認しておきたい。
2つの投射方式、「液晶」と「DLP」はどんな仕組み?
データプロジェクターの仕様表を見ると、上の方に「投射方式」という項目が必ず出てくる。基本的な仕様なのだろうと思いつつ、いまいち理解できないという人も多いだろう。
投射方式は主に「液晶方式」と「DLP方式」の2種類がある。液晶方式は、撮像素子として透過型液晶パネルを配置し、光源である水銀ランプからの光をその液晶パネルに通すことで像を生成する仕組みだ。今回取り上げた可搬型データプロジェクターでは、赤、緑、青の各色用に3枚の透過型液晶パネルを用意していることが大半で、液晶方式の通称である「3LCD」というブランド名もここに由来する。
DLP方式は米テキサスインスツルメンツが開発したもので、「DMD」という撮像素子を使う。DMDは微細な鏡を多数張り合わせたものである。例えばパネル解像度がXGAのDMDは1024×768ドット分の鏡を備えている。この1枚1枚の鏡で、ドット単位で光の反射を制御して像を生成する。DLP方式は、DMDを1枚使う単板方式と3枚使う3板方式があり、前者は可搬型のデータプロジェクター、後者は映画館向けなどの大型プロジェクターに用いられる。
一般にDLP方式は液晶方式よりコントラスト比が高い。また鏡を使うという仕組み上、同じ画像を長期間投影し続けても画面焼けが起こらない。一方で単板のDLP方式では、カラーフィルターを切り替えながら赤、緑、青、白の各色を順に表示する仕組みのため、画像のちらつきが起こる可能性がある。とはいえ近年は両方式とも弱点を補うべく改良を進めており、現行製品ならどちらを選んでもほぼ問題ないだろう。このほか、反射型液晶パネルを用いた「LCOS方式」もある。
プロジェクターの使い勝手を左右する要素
データプロジェクターで最も基本的な性能は輝度である。しかし近年は、メーカー各社が付加機能の充実で製品の差異化を図ろうとしており、製品選択のポイントが広がっている。社内でどうデータプロジェクターを活用しようと考えているか整理し、付加機能にも目を向けると納得の製品選びができる
主なデータプロジェクターメーカー
ソニー、セイコーエプソン、ベンキュー ジャパン、NECビューテクノロジー、三洋電機、松下電器産業、デル
輝度を表す単位「ルーメン」
一般にルーメンの値が高いほど、投射する画像がはっきり見えるようになる。また、部屋の照明を付けたままでも画像を見られるなど、データプロジェクターの用途も広がる。1ルーメンは、1本のろうそくを1m離れたところから見たときの明るさを示す
輝度と用途のめやす
「パネル解像度」の画素数を確認しよう
パネル解像度は、データプロジェクターが投射可能な画像の解像度を示す。パネル解像度を上回る信号が入力された場合、パネル解像度に合わせて圧縮して出力する。Excelで作成した細かい表やグラフなどを投射すると、ドットがつぶれて見づらくなる場合があるので注意が必要だ
台形補正を自動で行う製品が増加
データプロジェクターから上向きの角度で画像を投射すると、上辺が長い台形になって映し出されることが多い。ほとんどの製品はこれを補正する機能を持っている。高機能機にはセンサーで傾きを検知して画像を自動補正する機能を備えるものが増えている。会議室などでプレゼンを準備する際の手間が省ける
無線LAN機能のメリット
パソコンとデータプロジェクターをつなぐケーブルが不要になるので、ケーブルの持ち運びやプレゼン前のケーブル接続の手間が省け、発表者の席もデータプロジェクターの脇である必要がなくなる。一部メーカーの上位機種では、1台のプロジェクターで複数のパソコンの画像を分割表示したり、逆に1台のパソコンから複数のデータプロジェクターへ画像を同時に伝送したりする機能がある
液晶方式とDLP方式の仕組み
液晶方式は、赤、緑、青の液晶パネルに光を透過させることで像を生成。プリズムで3色を合成してカラー表示する。DLPは、1ドットごとに反射を制御できる微細な鏡の集まりである「DMD」で像を生成。赤、緑、青、白などの各色から成り高速回転するカラーフィルターで各色の像を順番に出力し、人の目の残像効果を利用してカラー表示している
最新データプロジェクター総覧
ここからは、主要各メーカーのデータプロジェクターを紹介する。基本性能を一通りそろえつつ価格が手ごろな製品、社外への持ち運びなども考慮してきょう体を軽くした製品、大人数を収容する会議室などでも使える高輝度の製品、仕様や付加機能において独自の特徴を備えている製品――の4分野について、それぞれ各社の製品を取り上げた。これ以外にも多くのメーカーから多数の製品が販売されており、必要とする輝度や予算などに応じて選べるようになっている。
なお、Webサイト「PCオンライン」(https://pc.nikkeibp.co.jp/)では、ここで取り上げた以外の製品も含め100機種近くのデータプロジェクターを紹介する予定だ。購入前の比較検討時に利用してほしい。
各製品の仕様の見方
価格が手ごろな製品(パネル解像度XGAで実勢価格20万円未満)
| 製品名 | メーカー | 価格 |
|---|
| 1800MP | デル | 直販価格8万9800円 |
| MP721c | ベンキュー ジャパン | 直販価格9万9800円 |
| VPL-EX3 | ソニー | オープン(実勢価格は約13万円) |
| U6-132 | 加賀コンポーネント | オープン(実勢価格は約13万円) |
| EMP-82 | セイコーエプソン | 20万7900円 |
| VT595J | NECビューテクノロジー | 20万7900円 |
きょう体の軽い製品(2kg未満)
| 製品名 | メーカー | 価格 |
|---|
| NP60J | NECビューテクノロジー | 39万6900円 |
| EMP-1715 | セイコーエプソン | 39万6900円 |
| 3400MP | デル | 直販価格12万4800円 |
| CP120 | ベンキュー ジャパン | 直販価格19万8000円 |
| TH-P1SD | 松下電器産業 | オープン(実勢価格は約15万円) |
| XJ-S35 | カシオ計算機 | 26万400円 |
| KG-PS125X | 加賀コンポーネント | オープン(実勢価格は約20万円) |
| VPL-CX21 | ソニー | オープン(実勢価格は約17万円) |
| TH-LB50NT | 松下電器産業 | 31万2900円 |
輝度の高い製品(3000ルーメン以上)
| 製品名 | メーカー | 価格 |
|---|
| LP-XU100 | 三洋電機 | 57万5400円 |
| EMP-1815 | セイコーエプソン | 52万2900円 |
| U7-137SF | 加賀コンポーネント | オープン(実勢価格は約39万円) |
| 5100MP | デル | 直販価格29万8000円 |
| TH-LB60NT | 松下電器産業 | 47万400円 |
| CP-X445J | 日立製作所 | 52万2900円 |
| MP770 | ベンキュー ジャパン | 直販価格19万8000円 |
| LVP-XD490 | 三菱電機 | 52万2900円 |
| VPL-CX86 | ソニー | オープン(実勢価格は約31万円) |
独自の付加機能を備えた製品
| 製品名 | メーカー | 価格 | 付加機能 |
|---|
| WT610J | NECビューテクノロジー | オープン(実勢価格は約35万円) | きょう体内部に複数の鏡を配置して、DMDからの光を内部で複数回反射させてからスクリーンへ投射する構造としている。これにより、一般のデータプロジェクターより投射距離が大幅に短く、壁際にデータプロジェクターを置いても大画面で投射できる。 |
| LP-XL40 | 三洋電機 | 52万2900円 | 投射用のレンズとして大口径の広角品を搭載することで、焦点距離を一般のデータプロジェクターより短くしている。重さ3.3kgなので、オフィス内での持ち運びも可能。電源を切った状態できょう体が動かされると警告を発する、防犯アラーム機能を備えている。 |
| SX50 | キヤノン | 62万7900円 | 撮像素子として一般的な透過型液晶パネルではなく、反射型液晶パネルを用いる「LCOS(エルコス)」方式を採用。LCOS(エルコス)方式では光が液晶パネルの駆動回路に遮られないため、一般の液晶方式より解像度が高く、画素間のすき間も見えにくくなっている。 |
| TLP-XC3000 | 東芝 | 59万6400円 | 300万画素のカメラモジュールを備えた書画カメラ付きのデータプロジェクター。紙の書類のほか、建物の模型や商品サンプルといった立体物を投射することもできる。アームは270度首振りできるほか、LEDの照明も備えており、暗いところでも撮影が可能だ。 |
| iP-30B | 日本アビオニクス | 48万900円 | 413万画素の書画カメラ付きデータプロジェクター。きょう体上部のふたを開け、複写機などと同じ要領でガラス面に書類や物体を置くことで撮影・投射できる。書画カメラで撮影した画像を、32枚まできょう体内部のメモリーに保存する機能を持つ。 |
| LVP-PK20 | 三菱電機 | オープン(実勢価格は約10万円) | 光源として、一般的な水銀ランプの代わりに白色LEDを採用。輝度は一般のデータプロジェクターより低いが、別売のバッテリーパック(約1万5000円)を取り付けると、コンセントのない場所でも画像の投射が可能になる。きょう体が小型軽量なのも特徴だ。 |